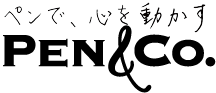Pen&Co.が手がけるスポーツ特化型メディア「Pen&Sports[ペンスポ]」の創刊(2023年7月26日)まであと3日となりました。ペンスポにコラムニストとして参画するスポーツジャーナリスト・佐藤貴洋(さとう・たかひろ)さんを紹介します。
元・日刊スポーツ記者。イタリアで中村俊輔番、広島でJ1、野球担当
佐藤さんは現在、神奈川県小田原市を拠点に活動するスポーツジャーナリストです。29歳で日刊スポーツ新聞社イタリア通信員になり、中村俊輔に密着。セリエAレッジーナでの3年間、すべての練習と試合(およそ150試合)を取材するためイタリア中を飛び回りました。帰国してからは広島総局に赴任、サンフレッチェ広島やプロ野球を担当しています。
以下は佐藤さん自身がつづったプロフィールです。ぜひお読みくださいませ。
佐藤貴洋さんのプロフィール

1973年5月、横浜市で生まれる。読売新聞社の記者だった父の転勤に伴って小学校は3校、中学校は2校に通う。高校は1校だったものの、自分の選択で大学は3校に通う「転校生人生」に。
ハマっ子を気取る間もなく3歳には引っ越し、幼稚園から小学校2年生までを愛知県春日井市で過ごす。
小学校3~4年生は秋田市。その頃からサッカー少年団に入ったが、サッカーを選んだ理由は今でも分からない。豪雪地帯の東北では、年間通して野球が出来る環境でもなかったからか、自然とサッカーを選んだのかもしれない。ちょうどキャプテン翼の連載が始まった頃で、サッカー人気の高まりはひしひしと感じた。
小学校5年生から中学校2年生までの4年間は茨城県水戸市で過ごす。翌1985年「科学万博つくば’85」開催に備え、父が水戸支局へと転勤となったからだった。中学でもサッカー部に入るが…学校も部活もかなり荒れていた。
3年生からは母の実家のある小田原に。人生初の勉強に取り組み、2学期には学年で一桁ぐらいまで順位を伸ばしたが、その中学校から35人ぐらいは入学したエリアトップ校の小田原高校の受験すら許されず、2番手の西湘高校を本命に私立高2校含めて3校を受験する羽目となる。
小田原駅からJR東海道線上りで1駅の「鴨宮」にある西湘高校に入学。入学直後、廊下の壁に貼られた高校受験の順位は確か「14番」。受験は満塁弾ぐらいの手応えがあったが、自分より上が「13人」いたことで、受験の悔しさをリセットできたことは良かった。
神奈川県の最西端学区にある2番手公立校は、居心地が良かった。当時11クラスあった中で、男子のみのクラスが1クラスあり、2年生時に当たった。修学旅行の新幹線車内はオトコだけ、文化祭もオトコだけ。後にも先にも人生唯一の男子クラス経験。異性の目がない集団は、ある意味快適だったが、できれば修学旅行や文化祭が開催された2年生で当たらなくても…とも思う。
校則も勉強も部活も上下関係も適度にゆるい西湘高校では、サッカー部に在籍しながら、楽しく充実した3年間を過ごした。
1浪後、平塚キャンパスが新設されて間もない神奈川大学国際経営学部に入学し、周囲に内緒で「再受験」を決意。慶應義塾大学環境情報学部を本命に「仮面浪人」をスタート。本番の小論文で会心の手応えと共に、湘南藤沢キャンパス(SFC)に合格。
念願の大学に入ったものの、サークル飲み、合コン、慶早戦、新宿・渋谷での遊びなど一通り大学生活を謳歌した後は、大学への熱量は徐々に冷めていった。「大学で何をやる」ではなく、「大学合格」自体が目標だったこともあり、完全に「対象喪失」で大学に通う目的を失っていたように思う。
そんな大学時代の一番の思い出は友人4人での欧州旅行。22歳だった1995年、人生初の海外旅行でイタリアの全てに衝撃を受けた。一つ一つの都市が醸す独特の空気感、郷土料理への強い誇り、身振り手振り交えた楽しそうな話術、そして熱狂的なサッカー文化-。
ヴェネツェアのユースホステル周辺を散策していたところ、サッカーのユニフォームを着た人が多く、聞けば近隣の街パドヴァでセリエA開幕戦があるとのことだった。チケットもないまま、興味津々の3人でスタジアムへと向かった。相手は名門ACミラン。1993年にバロンドール受賞、翌1994年ワールドカップアメリカ大会決勝ブラジル戦でのPK戦で、最終キッカーとしてPKを外し優勝こそ逃したが、たたたずまいが「世界一美しい敗者」として讃えられたイタリアの至宝ロベルト・バッジョが、移籍先のACミランのユニフォームに袖を通しての開幕戦(だったと思う…)。
チケットは既に売り切れだったが「チケットのない困った日本人」に見えたのだろう。イタリア人男性から「友人のチケットが余っているから、あげるよ」と奇跡的に3枚入手することに成功した。
試合は確か元イタリア代表レジェンドのDFフランコ・バレージのゴールでACミランが勝利したように思う。「あふれんばかりの熱量」に触れ、当時の日本に閉塞感を抱いていたこともあり、いつしかイタリアへ渡る決意をしていた。
ウンブリア州ペルージャにあるイタリア国立ペルージャ外国人大学で学びながら、イタリアレストラン、現地ガイド、通訳、日本人教授のサポート業務などをこなす。
転機は大学開催のフットサル大会だった。日本人チームの一人として出場、結果は散々だったが、男女約20名のメンバーにはサッカー関係者もいて、仕事を得るきっかけになる。
2001年夏、GK川島永嗣(元・日本代表)のパルマ短期留学時の通訳を務める。川島は当時、浦和東高校からJ1大宮入団1年目で将来を見据えて留学、パルマ下部組織のチームに交じり、ダイヤの原石発掘の大会「ヴィニョーラ・トーナメント」に出場した。驚異のスーパーセーブを連発し、大会最優秀GKに選出されるなど優勝の立役者となった。
わずか数週間だったが、紳士な対応、サッカーへの情熱、語学への渇望、異国の仲間との交流など、360°どこから見ても、プロフェッショナルな姿勢を貫く18歳を目の当たりにして、「年上も年下も、年齢は関係ない」と強く思うようになった。
優勝直後、永嗣から「ぜひ、これをタカさんに」と使用していたゴールキーパーグローブをプレゼントされた。お返しに、イタリア語の簡易辞書を渡したが、今では永嗣の方がイタリア語も堪能だろう。

29歳を迎え、日刊スポーツ新聞社イタリア通信員としてのオファーが舞い込む。MF中村俊輔が2002年日韓ワールドカップ日本代表に落選、セリエAレッジーナ(日刊スポーツ表記はレジーナ)に移籍が決まり、彼の担当として取材する仕事だった。「イタリア挑戦」に区切りを付けて日本行きの航空券を購入し、イタリアと別れを告げる数日前の話だった。
海のないイタリア中部ペルージャからローマ、ナポリを経由し、ブーツのカタチに例えられるイタリアの「つま先」に位置するレッジョ・ディ・カラブリア。ユーロスターで12時間ほどかけて、初めて降り立ったレッジョ・ディ・カラブリアの駅は、ペルージャにはない潮の香りが漂っていた。
鉄道駅のある中心街から7kmほどの空港近くにある練習場サンタガタに通う日々。通信員の仕事は多岐に渡った。早朝の現地新聞をチェックして選手、クラブに関する情報を集めて東京本社に共有する。当時、中村俊輔のセリエA移籍はドラマ性も高く、日本から多くの記者が現地取材に訪れていた。
南部レッジーナは、ほぼすべてのアウェー戦が飛行機移動だったため、ほぼ毎週のように飛行機でイタリア全土を巡れたことは、通信員ならではの特権だった。
当時、世界最高峰リーグの名を欲しいままにしたセリエAには、ロベルト・バッジョ、デル・ピエロ、マルディーニ、トッティらイタリア代表クラスをはじめ、ジダン、ロナウジーニョ、ベッカム、フィーゴ、レコバ、ロべカルなど名前を挙げたらキリがないぐらい世界各国のスーパースターが揃うリーグ。傾斜が急で、まるで真上から試合を観戦するかのようなACミラン、インテルの本拠地「サン・シーロ」をはじめ、イタリア全土のスタジアムで背番号「10」が躍動する姿は、同じ日本人として仕事を超えて誇らしく、贅沢な時間だった。
2004-05シーズン終了後にスコットランドリーグ・セルティックへ移籍するまでのレッジーナ在籍3年間、試合翌日以外は行われていた全ての練習と、リーグ戦、カップ戦の公式戦はもちろん、練習試合も含めると150試合ぐらいは取材しただろうか。
3年間追い続けた中村俊輔との思い出をひとつだけ明かすとすれば、「日韓W杯で履く予定だった幻の白スパイク」だろうか。1年目の秋だったか、練習場サンタガタから歩いて15分ほど、後にイタリア代表として通算116試合に出場した「マエストロ」アンドレア・ピルロが住んでいた出世部屋とも言える俊輔の自宅マンション。バランスボール、スーツケース、スニーカーとともに大量にあるスパイクの中から1足を選び、手渡された。
日韓ワールドカップで履く予定だったアディダスの白は、イングランド代表ベッカム、フランス代表ジダン、イタリア代表デル・ピエロ…。各国エースのみに託された白のスパイクを、未練を断ち切るかのように、私に渡してくれた。2006年ドイツワールドカップ出場を見据えるかのような、練習や試合では見せることのない表情だったことを覚えている。
その後はシチリア島にあるメッシーナのMF小笠原満男、カターニャのFW森本貴幸の取材を担当。拠点もレッジョ・ディ・カラブリアから美食の都パルマに移し、2006-07シーズン終了をもって、約10年間のイタリア生活に終止符を打ち、日本に帰国した。
日刊スポーツ広島総局の運動部記者に。私はJリーグ・サンフレッチェ広島をメーンに、プロ野球広島カープのサポート要員、そして高校野球、高校サッカー、高校ラグビーなどのアマチュアスポーツ全般を担当した。
帰国した2007年夏、Jリーグはシーズン真っ盛りで、ペトロビッチ監督率いるサンフレッチェは残留争いを繰り広げていた。サンフレッチェ取材は降格、1年でのJ1復帰など、ジェットコースターのような目まぐるしい展開で、担当記者にとっては盆と正月が一緒に来たような忙しさとなる。
FW佐藤寿人、MF柏木陽介、DF槙野智章の3選手には、原稿で何度もお世話になった。元イタリア代表FWフィリッポ・インザーギを憧れの選手に掲げる寿人は、インザーギさながらの嗅覚で得点を量産し、ユース出身の柏木と槙野は、それぞれ個性的なキャラクターと相まって、記事にしやすかった。
専門領域がサッカーの自分にとって、カープ取材は楽ではなかった。朝10時ぐらいの練習からナイター終了まで時間が長い。今でこそ野球も時間短縮の流れだが、当時は18時開始のナイターの終了時間は早くて21時30分。そこから取材して22時10分ぐらいには一面分の記事、雑感、速報など何本もの原稿を仕上げる。締め切り時間との戦いだった。
カープ取材では思い出に残る試合が3つある。
・2009年4月10日の中日戦:マツダスタジアム公式戦初開催で左右非対称で遊び心満載の新球場を心待ちにした観客の姿、アルバイトスタッフ、全てがゼロイチの瞬間を見届けられたこと。
・2009年10月10日の巨人戦:緒方孝市の引退試合。8回の守備から出場し、現役最終打席での右中間を破り両足をもつらせながらヘッドスライディングで三塁打、そして、次打者で捕手の後逸にすぐさま本塁を狙うが、届かずアウト。引退セレモニーでの「試合が終わればユニフォームが真っ黒な選手でありたいと…いつしかそのユニフォームが汚れることもなくなり」のセリフは、脳裏に焼き付いている。
・2010年5月15日の交流戦vs日本ハム:前田健太とダルビッシュ有のエース対決。将来、日本を背負うと見込んだダルビッシュが捕手のサインにあえて首を振りながら、打者前田に対して全ての球種を惜しげなく披露。結果は1-0。そのシーズン初完封となるマエケンに軍配が上がるが、両エースの投げ合いは、野球担当記者ではない自分もしびれた。マエケンは沢村賞に輝くおまけつき。
広島ではハードな日々を過ごした。特に夏。毎日ではないが、早朝から高校野球の取材&撮影してから、昼過ぎ開催のJリーグ広島の会場ビッグアーチに向かい、高校野球の記事作成と写真選び、Jリーグの取材&撮影をしてからカープ担当のサポートとしてマツダスタジアムへ向かう。マツダスタジアムでJリーグの記事作成と写真選びをしながらナイター取材。プロ野球の試合では必ずカメラマンがいるので、試合後は取材と記事制作…。
「Jリーグ広島のJ2降格から1年でのJ1復帰」「2009年1月12日広島皆実サッカー選手権優勝」、そして高校野球甲子園取材も。帰国直後は日刊スポーツ甲子園取材班の足手まといだった甲子園取材も、最後となった2012年春センバツでは、記者独自視線で自由にかける高校野球コラムを任せていただけたことは、本当に自信にもなった。
日刊スポーツでは多くの先輩記者やデスクから取材、記事のイロハを学ばせていただき、今でも感謝しかない。
広告代理店ではこれまでのスポーツ記事だけではなく、大学や企業の広報誌、情報誌、フリーペーパー、メルマガ、コピーライティングなど文系理系美術系医療福祉系問わずにライティングの幅を磨く。その後、不動産業界特化型のWeb制作会社でWebマーケティング&プロモーションを担当。
地元小田原の活性化に携わりたく2022年夏に独立。幼少期は父の転勤で、オトナになってからは自分の意思もあり4年に1度の五輪ペースで都市を渡り歩く人生。どこが地元なのか分からない中で、中学校3年生から大学時代の約10年間を過ごし、母の生まれ故郷で、両親の実家のある小田原を「地元」と自分で認定。これまで培った取材、ライティング、編集、企画、広告、Webサイト制作、ディレクションなど、小田原の活性化に携わりたく独立。
広島時代に大変お世話になった原田亜紀夫編集長から声がかかり、恩返しとばかりに即決。小田原アリーナを本拠地とするFリーグ湘南ベルマーレフットサルクラブを中心に「スポーツ×地方創生」を取り上げられたらと意気込んでいる。